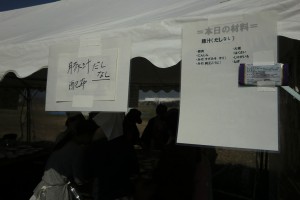平成23年度西尾市総合防災訓練が10月9日、西尾市一色町地内で開催されました。昨年度に引き続き、応急手当の基礎訓練として三角巾の使用方法について講習を行いました。
本当は、発災対応の実戦訓練をすべきなのに、こんな基礎講習をするのは本意ではないですが、日ごろお世話になっている西尾市防災課の依頼もあり、また、他の団体とのコラボの場として使えるということもあり、指導をしてきました。

西尾防災リーダ会と西尾市赤十字奉仕団のコラボ
写真は、参加した地元一色町の自主防災会のみなさんに、三角巾の折りたたみ方や提肘の方法を指導しているところです。ピンクの長袖ポロシャツを着ている女性陣が日赤奉仕団の皆さんです。従来は、西尾防災リーダー会が担当していましたが、指導人材を増やすために昨年度から日赤奉仕団の皆さんにも加わってもらっています。
日赤奉仕団の皆さんは、炊き出し訓練にも参加されていて、人員調整等に苦慮されていました。特に炊き出し訓練に関しては、正直なところ人手が余ってしまうという状況でした。毎日やっている炊事作業と変わらない部分は、手際よくサクサク進められますので、炊き出しの規模(必要人数)と自分たちが訓練のために参加する人数のギャップが相当ありました。
さらに、「わたしたちがやるから、そんなに大勢いらない」などと独占しようとする協調性のない団体がいて、少なくとも自分たちは割り当て人数の中で交代で体験しようというような調整もあったようです。
炊き出し訓練は、食べるものがない被災者へ食事を提供することを想定して実施する訓練です。いざというときは、どんな状況になるかわからないので、多数の団体のメンバーの混成で活動する場合もあります。団体間で協働できるよう平常時の訓練でチームワークの醸成・ネットワークの構築をしておく必要があります。今回の訓練もその絶好の機会です。特定の団体のための学習成果発表会の場ではありません。
自己アピールばかりで協調性のない団体とは、一緒にやれそうにありません。今回の訓練でまた、一緒にやれそうなところ/やりたくないところが見えてきました。
2011 年 10 月 9 日( 日 )23 時 59 分 |
コメント(1)
カテゴリー:講師・インストラクション
タグ:,愛知県, 西尾市, 西尾市総合防災訓練, 西尾市赤十字奉仕団, 西尾防災リーダー会
平成23年度西尾市総合防災訓練が10月9日、西尾市一色町地内で開催されました。昨年度に引き続き、食物アレルギー対応の炊き出し訓練がありました。
西尾市の総合防災訓練でアレルギー対応の炊き出し訓練を実施するようになったのは、昨年度の西野町小学校での訓練からで、今年度は2回目になります。NPO法人アレルギー支援ネットワークが中心になって、通常の炊き出しとの違い、注意点をレクチャしながら、炊き出し訓練の担当者と一緒に作ります。
昨年度は、アレルギー支援ネット、西尾市赤十字奉仕団、地元校区の自主防災会のみなさんが参加しました。しかも初めてということで、アレルギーの原因になる残留成分の検査キットを使用した調理器具の確認作業を事前に実施するなど、徹底した管理の下、炊き出し作業が進められました。
今年度は、さらに西尾市内にあるアレルギーっ子の親の会「アレっ子元気」のお母さん方も訓練に参加して、啓発に協力しました。また、自衛隊の炊飯車で豚汁を作るなど、新たな展開がありました。


参加された方にアレルギー対応の説明をするアレっ子元気、アレルギー支援ネットワークのメンバー
メニューは、特別なものではなく、どこでもよくやる「豚汁」です。ぱっと見では、普通の豚汁となんら変わりません。違いは、アレルギーの原因になる成分を含んだ材料を使わないこと。今回の豚汁では、出汁のもとになる合成調味料を使わないこと。成分表をよく見ると、アレルギーの方が食べてよいものかどうかの判断ができます。食物アレルギーじゃない人も食べられます。
使用した食材を明示すれば、アレルギー患者は食べられるかどうか自分で判断ができます。記載内容は正確性が求められます。記載漏れがあっては信用できなくなります。書き写すよりも袋や箱の成分表の部分を貼り付けるほうが確実。
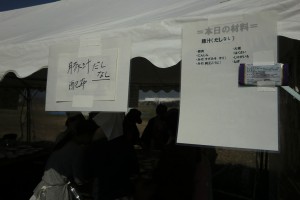
使用した食材を掲示
調理の過程でもきちんと管理するために、アレルギー対応のものは「だしなし」のラベル表示をしていました。

調理用バットに「出汁なし」のラベル表示

調理中の自衛隊さん

2台ある炊飯車の片方に「だしなし」のラベル表示

普通の豚汁と変わらない

興味津々で中を覗きこむ親子
東日本大震災では、多くのアレルギー患者が食べるものがなくて苦労しました。せっかく備蓄していた40万食近いアレルギー対応アルファ化米を、アレルギー患者に優先して配布するなどの配慮なく、被災者に配布してしまったというのが、現実。行政の無知を責めるのは簡単ですが、それでは事態は改善されません。広く一般に認知してもらう活動が必要です。
防災訓練の中でアレルギー対応の炊き出しを繰り返すことで、一般市民への啓発になると思います。今後も各地で実施していただきたい訓練です。
2011 年 10 月 9 日( 日 )23 時 58 分 |
コメント(1)
カテゴリー:視察
タグ:,NPO法人アレルギー支援ネットワーク, アレっ子元気, 愛知県, 西尾市, 西尾市総合防災訓練, 西尾市赤十字奉仕団
平成23年度西尾市総合防災訓練全体説明会が24日、市役所の会議室で開催されました。仕事の都合で参加できませんでしたので、防災課に出向いて概略説明を聞いて資料をいただいてきました。
8月11日の記事で報告したとおり、西尾防災リーダー会は、応急手当訓練を実施することで変わりありません。会場(屋外)のテントブースでやるので、自主防災会が町内に立ち上げる臨時救護所のイメージでやれればと考えています。もっとも、けが人の「メイク」をした負傷患者役を設定してやるような実践訓練ではないので、準備は楽ですが。
昨年に続き、赤十字奉仕団とのコラボでやりたいのですが、昨日の会議で日赤さんと顔合わせ挨拶や調整ができませんでしたので、福祉課へ出向き、要望を伝えてきました。
説明会で配布された資料に目を通していて、いくつか気になったので、以下、独り言メモを。
○会場
会場は、一色町細川三ノ割(一色町一般廃棄物最終処分場北)。津波被害を想定した訓練だから津波の影響を受けそうな湾岸地域を会場としたのだろうが、本当に発災した場合は、ここに災害対策本部を設営することなどありえないし、やはり、市内各地域をまんべんなく会場として利用する「持ち回り訓練」と割り切るしかないか。
○西尾市社会福祉協議会が参加
訓練項目に目新しいものは見当たらないが、災害ボランティア受付訓練に西尾市社協が参加するのは初めて。もっとも、合併前の一色町のときは一色町社協として参加していたのかもしれないが。西尾市社協は、これまで総合防災訓練に参加してこなかったことを思えば、一歩前進といえる。
西尾市地域防災計画(平成22年度修正)には、「一般ボランティアの受け入れは、社会福祉協議会と市民活動センターが中心となって担うものとし、災害の発生時には関係団体等の協力も得ながら、速やかに災害ボランティア支援本部が立ち上げられるよう準備に取りかかる。」とあるので、参加するのは当たり前の感があるが、何故だか、これまでは参加してこなかった。
近年の災害ボランティアセンターの運営は、どこも社会福祉協議会が中心になっており、地域防災計画に定義されていなくとも、市役所に言われなくても社協が率先して動くべきだとは思うが。現に、8月に訪れた石巻市災害ボランティアセンターでも岡山市社協からスタッフが派遣されていて、全社協、ブロック、県、市町村各級での社協ネットワークを生かして連携している。このネットワークから外れて、単独での対応などできるわけがないことを認識すべき。
○災害ボラセン設置場所
また、西尾市地域防災計画には、「災害が発生し、災害対策本部が設置された場合において、その指示により、避難所等におけるボランティア活動に関する情報を統括、管理し、ボランティアの配置調整等ボランティア活動拠点の活動を支援するため、総合福祉センター内に災害ボランティア支援本部を設置する。」とあるが、今回の訓練は、総合福祉センターをボラセン立ち上げ訓練の会場年として使用する予定はないようだ。総合福祉センターを会場とした立ち上げ訓練は近年一度も実施されていない。「持ち回り訓練」の会場でテントを張る練習をしている程度。いったい何時やるのだろう?
西尾市地域防災計画はインターネット上で世界中に公開されており、西尾市の体制は日本中の災害ボランティアが閲覧でき、いざと言うときの情報源として参考にしているはずである。いつまで計画にあわない訓練を続けるつもりだろうか?
○災害ボラセンサテライト
もっとも、今回の訓練会場で実施するのは、「災害ボラセンのサテライト」立ち上げ訓練だというのなら、話は別だ。西尾市と幡豆郡が合併して対象地域が広がり、総合福祉センターの1箇所だけで市内全域の災害ボランティア活動をカバーできるわけがないし、理屈後付けてもよいから、サテライト運営を地域防災計画に反映していただきたい。そのきっかけとなるなら、一色町の訓練会場で災害ボラセン立ち上げ訓練をするのも「有り」かもしれない。
災害ボラセンのサテライトは、いくつも事例がある。平成18年7月豪雨のときに岡谷市は湊小学校に湊サテライトを立ち上げたし、平成20年8月末豪雨のときに岡崎市は伊賀町西の広幡小学校南にサテライトを立ち上げた。はっきり明言していないが、東日本大震災においても、石巻市は似たような体制で運用している。石巻専修大学が災害ボラセンになっているが、石巻市に合併した旧牡鹿町では、牡鹿公民館で災害ボラセンを運営している。
2011 年 8 月 25 日( 木 )23 時 59 分 |
コメント(0)
カテゴリー:会議
タグ:,平成20年8月末豪雨, 愛知県, 西尾市, 西尾市地域防災計画, 西尾市役所, 西尾市社会福祉協議会, 西尾市総合防災訓練, 西尾市赤十字奉仕団, 西尾防災リーダー会
次のページ »