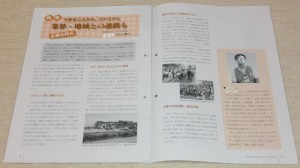愛知県防災局もついにTwitterで防災関連の情報を発信し始めました。
愛知県のウェブサイトの新着情報によると、Twitterで防災に関する情報の発信をしていくことになったようです。記者発表資料の再配信を予定していて、災害時は、愛知県から発表される災害関連情報を入手するのに便利になりそうです。平常時はウェブサイトでも情報を閲覧できるし、わざわざTwitterでということもないですが、日ごろから発信側も受信側も体制を整備して運用に慣れておくという点で、大切なことと思います。
防災関連のTwitterといえば、総務省消防庁が先行して運用しています。これまではウェブサイトの新着情報のページやRSS購読で情報をチェックしていましたが、Twitterに変わってからは、世の中の変化に置き去りにされている気がして、あせりも感じていました。
東日本大震災では、TwitterやFacebookが活躍して、発災時も有用なツールであることが認知されました。書店にはたくさんのノウハウ本が並んでいて、防災対策の一分野として情報ツールの使いこなしが必須となりつつあることを思い知らされます。
中央防災会議の「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」報告でも、「津波情報等の情報伝達体制の充実・強化」が挙げられており、具体策としてTwitterの活用を明示しているわけではないものの、有用なものは取り入れていくだろうから、受信する側の市民も個人個人が対応していく必要があるだろうと思う。
防災啓発をする立場でTwitterの導入を評価すると、やはり「デジタルデバイド」(ほとんど死語?)を感じて、やるせない気持ちになる。ITツールを使えない人たちが置き去りにされていくような気がしてならない。それでも、「減災」とやらの考え方からすれば、「すべてに行き渡らなくても、一部だけでも情報を届けられれば被害は減る」ということになるのだろう。
防災啓発のネタとして、「災害用伝言ダイヤル171」だけ言っていればよい時代は終わったと思う。ITツールによる情報収集・伝達も考えていく必要がありそうだ。そのためには、まず自分が使いこなさないと。まずは、モチベーションアップのために、防災啓発・災害対応のボランティア仲間から活用事例を聞くことからはじめたい。
総務省消防庁 @FDMA_JAPAN
http://twitter.com/#!/FDMA_JAPAN
愛知県防災局 @aichi_bousai
http://twitter.com/#!/aichi_bousai
2011 年 10 月 6 日( 木 )23 時 59 分 |
コメント(1)
カテゴリー:調査
タグ:,Twitter, 愛知県防災局, 東北太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会, 東日本大震災, 総務省消防庁
ポートメッセ名古屋で10月4日、国土交通省中部地方整備局の音頭で「東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議」が開催された。9月29日付のプレスリリース(ウェブサイト掲載)によると、かなり仰々しい体制で臨むようだ。「船頭多くして船…」になりそうな気配も。
それにしても、長野県勢はよく対応してくれたよなぁ~というのが感想。愛知・岐阜・三重・静岡は当然としても、長野県はほとんど支援側となって、「持ち出し」が相当あるのではないか。もちろん、飯田下伊那地域の天竜川沿いは被害予想が出ており、まったく無縁というわけではないことは知っているが、それでも、全体の比率から考えても、やっぱり割に合わない。これを縁に、名古屋圏とつながりを強くして、何らかの経済効果を期待したいということだろうか。
個人的には、長野県が加わってくれるのは大変ありがたいと思っている。行政の思惑とは関係なく、市民レベルの交流や支援を続けてきたのに加え、公的な動きが加われば、さらに強固な関係を築けるからだ。
これまで、NPO法人飯田ボランティア協会や長野県社協とともに、長野県各地の災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練に出かけ、関係作りに努めてきた。飯田市、高森町、軽井沢町、御代田町など。平成18年7月豪雨(長野県岡谷市の支援)もしてきた。平成20年8月末豪雨(愛知県岡崎市の支援)をしていただいた。飯田ボランティア協会の面々とは、東日本大震災の支援で、一緒に仙台市へも行った。いざというときに頼りになる存在だ。また、三遠南信災害ボランティアネットワークでは、浜松-豊川-飯田を核にして、災害ボランティアの交流活動も盛んだ。
新潟県堺の北信地域では豪雪対応も必要だ。飯山市社協が主催する「雪堀とうど塾」(除雪ボランティア講習と地域交流)にも2年ほど参加した。ここ数年参加できていないのが残念。この冬は、久しぶりに参加できたら…と考えている。飯山市社協さんには、企画をよろしくお願いしたい。
災害リスクは内容や規模が違っても、損得勘定抜きで相互支援できる(したいと思える)ような関係作りが、まず必要だ。交流が深まると、相手のよいところ、自分にはないもの、残して欲しいもの…、そういったかけがえのないものが見えてくる。そして、それを守りたくなってくる。
安曇野、伊那谷の豊かな自然、文化は、失いたくない。相互支援・交流を理由にして、長野へ出かけるのが楽しみになっている。リタイヤしたら、長野へ移住しようかなどと半分本気でで考えている。でも、「信濃の国」は未だになじめない(笑)。
2011 年 10 月 5 日( 水 )23 時 59 分 |
コメント(0)
カテゴリー:調査
タグ:,NPO法人飯田ボランティア協会, 三遠南信災害ボランティアネットワーク, 三重県, 仙台市, 信濃の国, 国土交通省中部地方整備局, 宮城県, 岐阜県, 岡崎市, 岡谷市, 平成18年7月豪雨, 平成20年8月末豪雨, 御代田町, 愛知県, 東日本大震災, 東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議, 浜松市, 豊川市, 軽井沢町, 長野県, 長野県社会福祉協議会, 静岡県, 飯山市, 飯山市社会福祉協議会, 飯田市, 高森町
8月4日の記事「西尾法人会会報誌のインタビューを受けました。」で紹介したインタビューを元に執筆された特集記事が掲載された西尾法人会会報(№121、平成23年9月発行)が完成しました。
インタビューを担当された株式会社エムアイシーグループの方から、できあがった会報を送っていただきました。ありがとうございます。
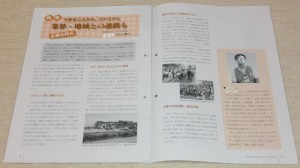
ページを開いた最初の感想は、「恥ずかしい!」の一言。大きな目立つ写真が載ってるので、もうちょっと小さめにして欲しかったかなと(笑)。あらためて読み返してみると、もっとあれこれ欲張ってもよかったかな。見開き2ページともなると、文字数もかなりたくさん詰め込めることがわかります。ちょっと空白部分が多めだし、その部分にBCP関連のお役立ち情報とかも記載すると、もっとよかったかも。 あまり、あれこれ書くと執筆者の批判になってしまうので、この辺で。地域防災をやってはいるものの、企業防災とは畑違いということでお許し願いたい。
同会報に掲載された会員情報によると、会員会社は1,648社。4月に幡豆郡と合併したとはいえ、この地域にはたくさんの企業があることを思い知らされた。インタビューでも訴え、記事にも記してもらったが、あえてここでも繰り返し訴えたい。
地域防災活動に腐心する身としては、地域連携を志向した企業防災に期待したい。これらの企業が、そこに勤める社員の一人ひとりが、BCP+CSRとして防災に取り組むと、この地域はどんなに災害に強いまちになることか。この地域に住み、この地域で働く人たちはたくさんいる。家庭・地域・勤務先でそれぞれの役割があり、防災でも切り話して考えられるものではない。
インタビューでは話題にならなかったことだが、どうか、移転(転出)は思いとどまっていただきたい。10月2日の記事「M9.0「3連動」津波…、-10月2日の中日新聞から」で紹介したように、巨大地震がこの地域を襲い、津波がこの地域を飲み込めば、壊滅的な被害が出ることは想像に難くない。東日本大震災を契機に工場やオフィスを移転した企業もあるが、どうか西尾を見捨てないで下さい。1,648社もの企業が転出できるようなところはどこにもないと覚悟し、この地で災害後にも生き残り、地域の人たちと乗り切る備えをしていただきたい。
生まれ育ったこの地が、見渡す限り何もない荒地になってしまうのは、あまりにも耐え難いのです。
2011 年 10 月 4 日( 火 )23 時 59 分 |
コメント(0)
カテゴリー:調査
タグ:,BCP, 愛知県, 株式会社エムアイシーグループ, 社団法人西尾法人会, 西尾市
« 前のページ
次のページ »